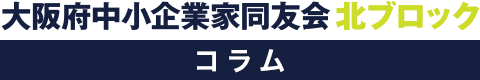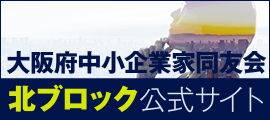パワハラと業務指導の境界線

はじめに
昨今、「ハラスメント」という言葉が多用されます。そのなかでも、私たち経営者にとって、最も頭を悩ませるのがパワハラではないでしょうか。
従業員に対し、すこしでも怒ると「パワハラ」と言われそうで、「従業員を叱れない」「従業員を指導できない」という悩みをよく聞きます。
パワハラの基準
パワーハラスメント。いわゆる「パワハラ」については、労働施策総合推進法第30条の2が次のように定義しております。
職場における「パワーハラスメント」とは、職場において行われる、
- ①優越的な関係を背景とした言動であって、
- ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
- ③労働者の就業環境が害されるものであり、
①~③までの要素を全て満たすものをいいます。客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。
この基準については、専門家の間では賛否のあるところですが、現時点(2025年現在)で法律がこのように基準を明確に示しておりますので、ここではこの基準に従って解説していきます。
①優越的な関係を背景とした言動について
当該事業主の業務を遂行する上で、当該言動を受ける労働者が「行為者に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係」(以下、「優越的な関係」と表記)を背景として行われるものをいいます。社長または上司から部下への言動が最もイメージしやすい関係ですが、例え同僚や部下の言動であっても、その者の知識や経験が豊富であり、その者の協力を得なければ仕事ができない場合なども、「優越的な関係」と言われます。その他、同僚や部下が集団で行なった言動も、その集団がいなければ業務が回らないなどの関係があれば、「優越的な関係」が認められやすくなります。
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものについて
社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又はその態様が相当でない場合が当ります。具体的には、人格を否定するような言動、暴力的行為、過大な要求や逆に過小な要求(いわゆる窓際に追いやるような行為)などがこれに当ります。
③労働者の就業環境が害されるものについて
当該言動により生じた身体的又は精神的に苦痛により、労働者の就業環境が不快なものとなったため、当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることをいいます。この判断においては、社会一般の労働者が、そのように感じる言動であるかどうかを基準とします。
まとめ
これら3つの要件のうち、1つでも欠けるとパワハラと認定されません。つまり、社員さんのことを思い、社員さんの成長を促すために業務指導を行なう限り、パワハラには当りません。
パワハラに当りかねない指導を推奨するわけではもちろんありませんが、パワハラに対し過度に委縮せず、適切な業務指導を行ない、会社を成長させましょう。